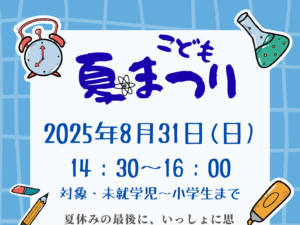西村久蔵「三浦綾子の洗礼を導いた『愛の鬼才』」
西村久蔵氏は、三浦綾子さんが洗礼を受けた時期に、病床の彼女を毎日のように見舞い、聖書を教えた人物。札幌北一条教会 長老、洋菓子の「ニシムラ」を創業。その生涯は、伝記小説「愛の鬼才」となった。
西村久蔵の救い
三浦綾子さんを受洗に導いた西村久蔵さんのお話を何度かしましたが、彼自身が洗礼を受けた時の話をしたいと思います。少年時代の西村久蔵は快活な性格でしたが、幼い弟の急逝、落第の屈辱、情欲の悩み、友人の死に接して、本を読み、物思いにふけることが増えました。18才の頃、後に著名になる若い高倉徳太郎牧師の教会で、毎週金曜日の求道者会に出ていました。北海道の寒い冬の始まる11月の金曜日の夜でした。
<その晩はイエス・キリストの十字架について、(高倉牧師は)訥々とどもりながら話されました。外は荒れております。風雪の音が不気味に聞える。聞く者は僅かに三人、寒々とした部屋の空気に小さく寄り合ってお話を聞いておりました。高倉先生は、イエスが十字架上で言われた七つの言葉について、お話をされ、特に「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」という聖言について、罪なき神の子イエスが、何故神に捨てられたと思われたかについての話をされました。聞いているうちに、その十字架を囲んでいた祭司、学者、群衆、そしてローマの兵士たちのイエスを罵っている有様が、目に見えるように思われました。そして十字架上のイエスの痛々しい姿が、私の心の目に、はっきりと映し出されたのです。 その時私は、この神の子を十字架につけて殺したものは人類の罪であり、その罪のさばきを贖うために、罪なきイエスが、苦しみ、捨てられ、死に給うたという、それまで何度か聞いた話が急転しまして、私、即ちこの西村という汚い罪人の犯せる罪や、心がイエスを殺したのだ、下手人は私であるという殺人者の実感、しかも、わが救い主、わが恩人、わが父を殺した恐ろしい罪をわが内に感じて、戦慄いたしました。…>
こうして久蔵は、翌日早朝受洗の希望を申し入れ、さらにその翌日の日曜日の礼拝において受洗したのである。」(第三章三)
「十字架の言は、滅び行く者には愚かであるが、救にあずかるわたしたちには、神の力である。」 (Ⅰコリント1:18)
長谷川与志充、三浦綾子読書会牧師会資料「三浦綾子文学講座 「愛の鬼才」②」。筆者が古い言葉を変更するなど編集し、背景を加筆して掲載。参照:三浦綾子「愛の鬼才 西村久蔵の歩んだ道」第三章 三
西村久蔵さんは、聖書を通してありありと十字架のキリストを心に感じ、自分の罪に打ちのめされ、その罪の赦しを与える生けるキリストを心に信じて、キリストのもとに行きました。[8]
試練の中で神の力を経験する
最近、三浦綾子さんの「愛の鬼才」という作品を読んでいます。北海道で活躍したクリスチャン実業家の西村久蔵という人物の伝記小説で、三浦綾子が受洗した時期に、毎日のように病床の彼女を見舞って聖書を教えた人物です。
(三浦綾子「愛の鬼才」第4章に基づき、筆者がまとめ直した。)
久蔵は18才で洗礼を受けましたが、キリスト教への偏見が強い時代でした。久蔵は自分の信仰を隠しませんでしたが、祖父の西村真明は儒教学者であり大のキリスト教嫌いだったので、洗礼を受けたことを決して明かしてはならないと父に命じられました。
受洗の2年後に、久蔵は四国の祖父を訪ねます。ところが、ちょうどクリスマスになり、当時東京で出席していた教会からのクリスマスの案内状が、東京の下宿先から祖父の家に転送されてきて、久蔵の入信が明らかになり、祖父は激怒します。
「久!お前は誰に断って、ヤソを信じた?ご先祖に対してはむろんのこと、西村家の今後にとっても、未曽有の一大事である。返答によっては、決してただではすまさぬぞ!」祖父の気迫に、久蔵は返す言葉もなく、平身低頭して主に助けを祈るばかりでした。
「久!キリスト教は忠孝を基本とする儒教と相いれない。わが西村家には、ヤソは一歩も踏み入れさせてはならぬ。どうじゃ、久!今この祖父の面前で改宗するか。改宗しなければ、勘当じゃ!どうじゃ!」久蔵は、祖父の怒りにこもった真実と、主イエスが自分を愛して下さる真実に挟まれて、答えるすべがありませんでした。「申し訳もございません。…ぼくはキリストに救われた者です。キリストに赦された者です。」祖父・真明は、刀があれば切り付けんばかりの剣幕で、3時間余りも叱り続けたといいます。
久蔵は一晩中眠ることができず、祈りに祈りました。翌朝、祖父は再び久蔵を叱責しますが、昨夜の勢いはありません。「久、ヤソは親不孝の教えであろう。<我よりも父や母を愛する者は、我にふさわしからず>と書いてあると聞いた。」その声には、キリスト教を知りたい思いが生まれていました。「おじい様、キリスト教は決して親不孝の宗教ではありません。十戒には<汝の父母を敬え>とあります。しかし、父母以上に神を敬うことが、人間の生きる土台なのです。神の教えに従って生きる者が父母を愛する時、その愛はもっと深く、もっと熱く、もっと真実になるのだと聞いております」。
「ふーむ。では、ヤソの教会では男も女もなれなれしく語り合い、風紀を乱していると聞くが、それはどうか」――「はい、それも世間の誤解だと思います。キリストはこう言っています<情欲を抱いて女を見る者はだれでも、心の中ですでに姦淫を犯したのです>と。」これを聞いた真明は、「これは手厳しい。儒教の教えよりもはるかに厳しい」と納得します。
「なるほど、聞けばヤソにもよいところがある。だが、ヤソは位牌を守るという重大な勤めをないがしろにするというではないか。ヤソは祖先をどのように祀るのじゃ。」久蔵は答えられません。「それ見よ、このわしが死んだとしても、線香一本お前は上げてはくれまい。何と情のないことじゃ。」――久蔵は「キリスト教は決して死者を拝みません。しかし、死んだ人を祈りの中で思い出し、敬い、愛します」と言って、祖父のために日頃祈っている祈りを明かします。真明は、久蔵が毎日1時間近く祈り、真明のために毎朝欠かさずに祈っていることを知って、態度を変えます。
その日から10日10夜、真明は、久蔵の入信の動機、罪について、キリスト教について、ひたすら質問をして、久蔵の言葉に聞き入りました。「神は人間がつくったものではないか」「神が人間を作った目的は何か」「神が愛ならば、なぜ疫病や災害が正しい者に襲うのか」「聖書はいつ誰が書いたのか」「聖書の最も重大な教えは何か」「なぜ日本古来の宗教ではなく、キリスト教でなければならないのか」「仏教とキリスト教の決定的な違いは何か」「天皇に忠実であることと、キリストを信じることは、相反するものではないか」…。
そして、正月七日の夜、真明は最後に尋ねます。「お前はこの10日間、ただの一度もわしの質問に答えられなかったことはない。わずか20歳のお前が、受洗して2年だというのに、そうした知恵をどこから得たのか」――久蔵は、主イエスの言葉を思い出して、学問の深い祖父・真明の質問にことごとく答えることができたのは、まさに聖霊によるものだと確信し、身体が震えるのを感じました。
真明は、上機嫌で久蔵に入信を許し、その後1週間、久蔵を連れて人々に紹介して、「この孫は本物のヤソぞ」と誇ったと言います。さらに、岡山や倉敷の当時の著名なクリスチャンを訪ねて、久蔵を紹介してくれました。
三浦綾子「愛の鬼才」第4章[①]
受洗して間もない久蔵にとって、祖父の怒りは試練以外の何者でもなかったはずです。しかし、その試練は、むしろ神の御業を経験する機会となり、自分を越えた神の力に驚嘆し、さらに神を信頼する契機となっていきました。
戦時下の歩み
【西村久蔵と岡藤丑彦】 西村久蔵は、戦時中に徴兵を受けて中国で任務に就きます。
(三浦綾子「愛の鬼才」第10章より、筆者がまとめ直した)
彼の高校時代の親友でクリスチャンの岡藤丑彦は、西村を訪ねて中国に行きます。「西村、君は軍隊に籍があったばかりに、殺戮の戦場に立たねばならん。私はその友人として、君の罪の償いのために、中国の人々に奉仕するために、中国にやってきた」。岡藤は、ある人物の紹介で、中国人が経営する工場の顧問になります。岡藤は中国の服を着て、日本人の特権を放棄して、中国の人々と同じ苦しみを共に味わいます。しかし、工場の職員たちは、日本人である岡藤に近づく者は一人もありませんでした。
ある夜、彼が家にいると、表が騒がしくなり、突然玄関が開き、若い女が真っ青な顔で彼の家に飛び込んできました。岡藤は万事を察して、廊下の戸を開けて女を逃がしました。続いて、日本兵が酒に酔い、刀を抜いて家に上がってきました。中国服を着た岡藤を中国人だと思い、蹴りを入れ、刀を振り上げました。岡藤が「主よ、御心のままに」と祈った瞬間、顔と首に衝撃を感じ、彼は気を失います。日本兵は彼を峰打ちにして(刃の裏で打った)のでした。岡藤は、気が付くと人々が取り囲んで騒いでおり、日本兵は憲兵に連行された後でした。岡藤は主に感謝し、日本兵の罪を人々に心から詫びました。翌日、岡藤が痛みをこらえて工場へ行くと、多くの中国人が礼をしてきます。彼の部屋には青年たちが入れ代わり立ち代わりやってきて、それ以降、彼の生活は一変します。岡藤は、多くの学校から日本語教師として礼を尽くして迎えられ、住まいを提供されました。軍務についている西村久蔵と共にキリスト教の家庭集会を開き、「そこには世の常ならぬ平安があり、主の恵みは満ち溢れていた」といいます。
中国での日本人の悪行を見た岡藤は、ひそかに久蔵に語りました。「神は日本を懲らしめる。だから必ずこの戦争は敗れる」。▼西村久蔵は、戦後、戦争に加担した罪を激しく悔いました。彼自身は直接人を殺さず、中国の人々を愛しました。しかし、国家の罪が教会と相いれなくなっても、教会の立場を明確にせず、たとえ逆賊と呼ばれ死刑になろうとも非戦の立場を貫くことをせず、戦争に加担したことを深く悔いて、悔悟の人生を送りました。[①]
三浦綾子「愛の鬼才―西村久蔵の歩んだ道」第10章
https://morishita.merry-goround.com/blog/okafuji-1/
2テモテ3:12 いったい、キリスト・イエスにあって信心深く生きようとする者は、みな、迫害を受ける。
岡藤が経験し、西村が悔いたように、クリスチャンがキリストにあって生きる時、多かれ少なかれ、そこには十字架と迫害があり、時代によってはそれは命がけの熾烈なものになります。現在の日本には命がけの迫害はありませんが、日常生活の中で私たち一人一人に与えられた苦難・不条理を、キリストに従ってどのように向き合うでしょうか。
聖書とのつながり:礼拝メッセージでの引用
[①] 三浦綾子「愛の鬼才」第4章
[①] 三浦綾子「愛の鬼才―西村久蔵の歩んだ道」第10章
[8] 長谷川与志充、三浦綾子読書会牧師会資料「三浦綾子文学講座 「愛の鬼才」②」より。筆者が古い言葉を変更するなど編集し、背景を加筆して掲載。参照:三浦綾子「愛の鬼才 西村久蔵の歩んだ道」第三章 三