出エジプト20:1-20「十戒:神の宝の民として」
2025年10月19日(日) 礼拝メッセージ
聖書 出エジプト20:1-20
説教 「十戒:神の宝の民として」
メッセージ 堀部 舜 牧師

1神はこのすべての言葉を語って言われた。
2「わたしはあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出した者である。3あなたはわたしのほかに、なにものをも神としてはならない。4あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水のなかにあるものの、どんな形をも造ってはならない。5それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。…7あなたは、あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。主は、み名をみだりに唱えるものを、罰しないでは置かないであろう。8安息日を覚えて、これを聖とせよ。9六日のあいだ働いてあなたのすべてのわざをせよ。
12あなたの父と母を敬え。これは、あなたの神、主が賜わる地で、あなたが長く生きるためである。13あなたは殺してはならない。14あなたは姦淫してはならない。15あなたは盗んではならない。16あなたは隣人について、偽証してはならない。17あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ろば、またすべて隣人のものをむさぼってはならない」。
18民は皆、かみなりと、いなずまと、ラッパの音と、山の煙っているのとを見た。民は恐れおののき、遠く離れて立った。19彼らはモーセに言った、「あなたがわたしたちに語ってください。わたしたちは聞き従います。神がわたしたちに語られぬようにしてください。それでなければ、わたしたちは死ぬでしょう」。20モーセは民に言った、「恐れてはならない。神はあなたがたを試みるため、またその恐れをあなたがたの目の前において、あなたがたが罪を犯さないようにするために臨まれたのである」。
出エジプト20:1-5,7-9,12-20
【ファミリーコンサート】 先週のファミリーコンサートで祝福された時を持てました。皆さんの参加・出演・ご奉仕・背後の祈りに感謝いたします。私は司会として前から見ていましたが、皆さんの笑顔から、心を開いて楽しんでくださっているのを感じて、喜びに満たされました。この教会が地域に根差して歩み、ご家族や地域の方々の祝福の通路となれるように願います。
今日の聖書の箇所は十戒です。神様が選ばれ、宝の民とされたイスラエルに与えられた、神の民の設計図のような掟が十戒です。教会がこれに従って歩む時に、私たちが祝福され、人びとに祝福をもたらす者となります。
聖書の背景
十戒を単なる「社会生活のルール」のように見てしまうと、信仰上の本質を見落としてしまいます。▼十戒は、神様とイスラエルの契約の形式で書かれています。「全ての人が結ぶ契約ではなく、奴隷状態から神に救い出された神の民が結ぶ契約」です。▼それはある意味で結婚の契約に似ています。特定の相手と結ぶものであり、相互の関係とコミットメントの上に成り立ち、関係性を維持するために必要なものです。▼律法を一言一句を守る行いの面で従おうとするならば、私たちは限界にぶつかり倒れるほかありません。しかし、私たちを招く神の愛に心を留めて、十戒の示す道に従い、一歩一歩悔い改めと信仰をもって、愛の心という内面の基準で従っていきたいと願います。
【シナイ山】 イスラエルの民は、10の災いと過越を経てエジプトを脱出し、海を通って荒野の旅を続け、マナの奇跡、岩から水が出る奇跡を経験します。19章では、エジプトを出た第3の月にシナイの荒野に着きます。これは数カ月前にモーセが燃える柴の中の主に出会ったシナイ山(別名ホレブ山)のある場所です。モーセが一人で召命を受けた場所で、今度は200万人とも言われるイスラエル人を連れて、神の民となる契約を主と結びます。

【宝の民】 19章に、十戒の土台となる、神の民への招きの言葉があります。
出エジプト19:4『あなたがたは、わたしがエジプトびとにした事と、あなたがたを鷲の翼に載せてわたしの所にこさせたことを見た。
契約の土台は、「神様がなされたこと」です。神様がエジプトから救い出された救いの御業を前提として、イスラエルと契約を結ばれます。彼らはすでにエジプトを離れて、荒野の旅に出て一日一日を主により頼んで生き始めている人々です。▼神様は、父が子を愛するように、夫が妻を愛するように、彼らを「宝」とすると言われます。
出エジプト19:5-6 『それで、もしあなたがたが、まことにわたしの声に聞き従い、わたしの契約を守るならば、あなたがたはすべての民にまさって、わたしの宝となるであろう。全地はわたしの所有だからである。6あなたがたはわたしに対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう』。
神がイスラエルを「ご自分の民」として選ばれる目的は、彼らが神に仕える「祭司」として国々のためにとりなす者となることであり、また、神のために取り分けられて神の素晴らしさを反映する「聖なる民」となることです。
神様はこの時、民を聖別して山の麓に集め、「雷鳴と稲妻と厚い雲」、地震と「火と煙」を伴ってシナイ山に現われ、モーセと語られました。[1]
私たちの神との出会いは、自然現象を伴って劇的な顔と顔を合わせるものではありません。しかし、神の御業を経験し、聖書を通して個人的に神の語りかけを聞く聖霊体験を通して人格的に神を知る時に、神の契約は私たちの心に刻まれて、私たち自身のものとなります。
■十戒
【神への愛と人への愛】 それでは具体的に十戒を見ていきます。▼十戒は前半と後半に分かれます[2]。前半は神様との関係、後半は人間との関係です。それはちょうど、主イエスが聖書全体を要約した教え「心を尽くして主を愛し」「隣人を自分自身のように愛しなさい」という2つの聖句と対応します。
◇第1戒:ほかの神があってはならない
第1の戒めは、「ほかの神があってはならない」です。2節は、契約を結ぶ両者を明示します。
20:2 「わたしはあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出した者である。」
この救いの宣言に基づいて、主だけを神とすることが命じられます。
20:3 あなたはわたしのほかに、なにものをも神としてはならない。
エジプトでもカナンでも多くの神々がありました。しかし、主が彼らを奴隷生活から救い出したので、主だけを神とするように招かれました。「イスラエルよ、あなたはわたしが選び、エジプトから救い出したのだ。わたしの民となりなさい」と言われます。最強の国であったエジプトの王と軍隊を打ち、海を分け、荒野で200万もの民を養うことができるのは、まことの神のほかにありません。▽それはちょうど、身分が低く苦しんでいた子どもを、偉大な王様が養子として引き取るようなものです。「わたしのほかに、なにものをも神としてはならない」とは、王が「末永くわたしの家に住みなさい」と招いて下さっているようなものです。
【会社での出来事】 私は神学校に入る前に、IT企業で3年間働きました。会社は新宿にあり、新年最初の出勤日に、会社の皆が明治神宮に初詣に行くことになりました。私は最初はどうすればよいか戸惑ったのですが、丁寧に役員にお話しすると理解してもらえて、私は初詣には行かずに、その代わりに会社で留守番をして、システムの緊急時対応を買って出ました。一人だけ初詣に行かなかった私はどう見られるか不安もあったのですが、むしろ新年早々のお楽しみ行事にも参加せずに、自分から仕事を買って出たことが、同僚たちに大変喜ばれました。初詣から帰ってきた同僚たちが、留守番をしていた私を笑顔でねぎらってくれたことが、楽しい思い出です。
20:3 あなたはわたしのほかに、なにものをも神としてはならない。
クリスチャンとして主だけに仕える使命を、社会との対立ではなく、奉仕の機会として用いるなら、私たち自身にとっても、周囲の人たちにとっても祝福となることを学ぶ機会となりました。

◇第2戒:偶像の禁止
第2の戒めは、偶像の禁止です。
20:4-5 4あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはならない。…どんな形をも造ってはならない。5それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。…
【礼拝の対象】 ここで言われている偶像は、他の神々の像であり、礼拝の対象とされるものを指します。この戒めは、人間や天使の像や絵をことごとく禁止しているのではありませんし、それが礼拝所に置かれていればただちに偶像と呼ばれるわけではありません。たとえば、出エジプト記でこの後建てられる幕屋には天使ケルビムの像があり、幕にもケルビムの模様が織り出されていました[3]。モーセの幕屋に天使の像があったのです。しかし、ケルビムの像を礼拝するわけではありませんので、それは偶像とは呼ばれませんし、罪でもありません。それを礼拝の対象としたり、誤用したりするときに、問題となります。
偶像崇拝の核心は、私たちの心がどこにあるかにあります。▼私たちは何に信頼しているでしょうか?人間の助けに頼っているでしょうか?経済的なものに頼っているでしょうか?――イスラエルの民は、神に信頼してエジプト王に対抗し、エジプトの軍隊を恐れずに脱出し、命を支える食糧も水も神からの供給に頼って荒野を旅しました。これは、神に信頼することを教えています。▼また私たちは何を夢見て、何を求めているでしょうか?自分自身の成功・繁栄でしょうか?それとも、神が下さるビジョンに――貧しい人が顧みられ、全ての人が生かされ、神の正義と公正が支配する神の国のために――献身しているでしょうか?それこそ、十戒と律法が指し示す神の義が支配する社会です。
◇第3戒:御名を聖とする
第3の戒めは、「主の御名を唱える」ことについてです。
20:7 あなたは、あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。
これは特に裁判の時などに、主の御名によって誓うことに関して言われています。しかし、それだけでなく、幅広い場面に当てはまります。英語などでも「神様」とか「イエス様」という言葉を軽く口走るような表現がありますが、神様のお名前を呼ぶことは、神に呼びかけ、神様の応答を求めることで、何の気なしに口癖のように言ってはならない言葉だと思います。▼より身近には、教会で青年たちが祈ったり讃美したりする時に、「みんなが祈るから」「みんなが歌っているから」といって、神様が答えて下さるという信仰がないのに神様への祈りの言葉を口に出すことも、厳密には「みだりに主の名を口にする」ことになるのではないでしょうか。▼恐れと信頼をもって、主の御名を唱えることを証ししてまいりましょう。
◇第4戒:安息日
安息日に関しては、今年2月に里子牧師から丁寧にメッセージがありました。それは、「何もしない日」ではなく、神のために取り分けられた日です。
イザヤ58:13-14 「13もし安息日にあなたの足をとどめ、わが聖日にあなたの楽しみをなさず、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を尊ぶべき日ととなえ、これを尊んで、おのが道を行わず、おのが楽しみを求めず、むなしい言葉を語らないならば、14その時あなたは主によって喜びを得、わたしは、あなたに地の高い所を乗り通らせ、あなたの先祖ヤコブの嗣業をもって、あなたを養う」。…
安息日のモデルは、神様ご自身が創造の7日目に安息されたことでした。神様は疲れることのない方です。その神様が7日目に安息されたことに、安息日の目的があります。多くの人が、実際的な休息とリフレッシュを必要としています。しかしそれだけではなく、日々のなすべきことに追われる生活から離れて、神様のために時間を取り、御言葉に聞き、主を見上げ、神の業に仕えること。これが安息日の目的ではないでしょうか。
(※以下の証しでは、「安息日」を主日に置き換えています。安息日と主日の関係については、他のメッセージで繰り返し述べているため、ここでは説明は省略します。)
【主日の奉仕】 ある友人が、能登の被災地に行った時の話をしてくれました。彼は仕事で能登に行きました。彼は日曜日の礼拝を自分の教会で守ることを本当に楽しみにしていて、土曜日に仕事を切り上げて、とんぼ返りで東京に戻りました。仕事のお客さんからは、日曜日は能登でゆっくりして食事でもしないかと誘われましたが、彼がクリスチャンであることを知っていたので、理解してくれたそうです。そのお客さんの家に招かれて行った時に、高齢のおばあさまがおられて、話になり、彼が日曜日に東京に帰ることを聞いて、「あんたは日曜日に帰るのかい。私も日曜日には行く所があるんだよ。とっても楽しいんだよ」と言われました。彼は感じるところがあって、おばあさんに尋ねてみると、「私は日曜日に教会に行くんだよ」とおっしゃったそうです。能登に震災復興のボランティアで行っている青年たちが、日曜日にボランティアでご高齢の方たちにお茶を出してお迎えしていて、いろいろな話ができてとても楽しい、毎週行っているとのことでした。
このボランティアの青年たちの働きは、ただの「休息」ではありません。むしろ活発な働きを伴うものですが、神の御心に聞き、神に喜ばれることを行うという意味で、安息日の精神を行い、「安息日を聖とする」生き方ではないかなと思います。(参照:メッセージマルコ2:23-3:6「安息日の主」、マタイ12:1-14「安息日であっても」)
◇第5戒:父母を敬え
第5戒からは、人間同士の間の教えです。
【古代の法律】古代の法律は「パラダイム法」と呼ばれて、全ての状況を網羅しようとする現代の法律とは異なり、「こういうケースではこのようになる」という一つのサンプルを示すだけで、人びとはその枠組みを自分で常識に従って適用していくべきものでした。例えば、「盗まれた牛や羊は弁償しなければならない」22:1と言われていれば、そこにしるされていない山羊を盗んだ場合も、弁償しなければなりません。「父母を襲った者は死刑にされる」21:15とあれば、祖父母を襲った時にも何らかの罰を受けました。そこにはっきりと記されていない事柄にも適用されたのが、古代の契約でした。▼十戒に関しては、「父と母を敬え」という戒めは、祖父母を含む先祖にも適用されます。
その最初が「あなたの父と母を敬え」です。▼日本には、忠孝を重んじる儒教由来の伝統があります。かつてキリスト教への批判として多かったのは、キリスト教が先祖崇拝をしないことから、「先祖を大事にしない宗教だ」という批判でした。これは誤解と偏見もありましたが、そう言われても仕方のない側面もあったと思います。▼日本のキリスト教は明治期に欧米から入ってきました。先祖崇拝を警戒するあまり、家族の繋がりを断ち切ってしまうような改宗のあり方がありました。それは、個人主義の強い欧米の文化を反映したもので、聖書のユダヤの文化と異なり、日本の文化にも合わない部分があったとも言われます。[4]▼しかし、聖書の神は「父と母を敬え」と言われました。(この戒めは、上述のように古代の法律の解釈法に従えば、祖父母を含む祖先にも適用されます。)イスラエル民族は自分の家系を大切にし、先祖の記憶を伝え続けた民族です。たとえば、創世記でも、父祖たちの記憶が何千年も語り継がれ、敬われました。私たちクリスチャンは、先祖を神として崇拝してはいけませんが、父母や先祖を大切にしなければなりません。死者の復活の希望は、死を越えて、私たちを祖先たちと結びつけます。▼忠孝を重んじる文化は、現代の日本にも根付いていると思います。現代は家族のつながりが希薄になり、宗教の役割が再び問われる時代です。家族の時間を大切にし、持続可能な形で父と母を大切にし、先祖の記憶を大切にすることは、私たちがクリスチャンとして知恵をもって取り組むべき役割と言えるのではないかと思います。
【墓前礼拝】 今年の1月に私たちは両親と兄の家族と共に、祖父母の墓を訪ねて、聖書を読み・讃美歌を歌って墓前礼拝をしました。家族の思い出を振り返るとても良い時間になり、そこから家族の歴史を知る貴重な機会になりました。
20:12 あなたの父と母を敬え。これは、あなたの神、主が賜わる地で、あなたが長く生きるためである。
祝福の約束を伴う最初の戒めとして、この戒めに心を留めて参りましょう。
◇第6戒:殺してはならない
第6戒は、「殺してはならない」です。
【主イエス】 主イエスは、「殺してはならない」という戒めを、ご自分の権威をもって、「兄弟に対して怒る者」「兄弟にむかって愚か者と言う者」「ばか者と言う者」に対しても、この戒めを押し広げて適用しました。殺人という行為だけでなく、その原因となる心の中の敵意・悪意を指摘されます。▽誰でも自分が攻撃されたり、大切にしているものが侵害されたりすると、反射的に怒りの反応が出て、防御的になろうとします。しかしその感情を反射的に攻撃的な言葉で表現するかどうかは、その人の責任です。毒のある感情を毒のある言葉で表すなら、それはその人の罪となります。その感情を、神の前に持っていき、主イエスの十字架の血をもって洗い清めて頂く必要があります。▽反射的に抱く怒りや悪い感情を、抱き続けるかどうかは、その人の責任です。怒りや嫉み・恨みといった苦々しい思いを持ち続けることを、主イエスは戒められました。
◇第7戒:姦淫してはならない
第7戒は、「姦淫してはならない」です。主イエスはただ不貞の行為だけではなく、その根源にある汚れた思いを罪に定められました。「だれでも、情欲をいだいて女を見る者は、心の中ですでに姦淫をしたのである。もしあなたの右の目が罪を犯させるなら、それを抜き出して捨てなさい。五体の一部を失っても、全身が地獄に投げ入れられない方が、あなたにとって益である。もしあなたの右の手が罪を犯させるなら、それを切って捨てなさい。五体の一部を失っても、全身が地獄に落ち込まない方が、あなたにとって益である」と言われます。主イエスの言葉は、この誘惑が厳しく、激しい戦いがあることを示しています。異性に惹かれることは自然なことですが、それは適切な形に留められなければなりません。罪を犯す以前に、心の中で誘惑を受けるような状況を避けるべきです。
◇第8戒:盗んではならない
第8戒は、「盗んではならない」です。教会に来ている人が盗みや万引きをすることは、ありますが比較的少ないでしょう。聖書ではしばしば「異なる秤」が非難されます。商売人が枡を小さくしたり、秤の重り石の重さを変えたりして、相手を騙して利益を得ることが非難されます。以前、自動車修理会社が車をわざと傷つけて修理代を請求した事件のように、様々な不正やごまかしは、この世に溢れています。▽仕事上の強い立場を利用して、契約外の仕事を要求したり、サービス残業を要求したりすることも、ある種の盗み・搾取と言えます。▽身近な例では、パソコンのソフトウェアには海賊版やグレーゾーンのライセンス商品があふれています。コピー商品に手を出すことも、盗みの一種と言えます。

◇第9戒:偽証してはならない
第9戒の「偽証してはならない」は、主には裁判での証言が考えられますが、より広い場面に適用されうると思います。他人に対して正しい言葉で語っているでしょうか。職場や近隣のうわさにのらないこと。時には自分で分かっていて悪意のある言葉を言ってしまうケースもあれば、うっかりして/気付かずに言ってしまうこともあります。「ことば数が多いところには、背きがつきもの。自分の唇を制する者は賢い人」とあります(箴言10:19)。言葉の罪を避けるために、口を慎むことが基本的に大切なことです。▽キリスト教の幅広い伝統で、相手が反論することのできない、その人がいない場所で誰かを批判することは、愛に反する罪として、避けるべきこととされてきました。徳を立てる言葉を語り、偽りの証言に陥りかねない噂話は慎むべきです。
◇第10戒:貪欲
第10戒は、心の中の行き過ぎた貪欲な欲望を戒めます。「あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ろば、またすべて隣人のものをむさぼってはならない」(17節)。他人の物を欲しがり、要求するのは明確な律法違反です。この戒めは、要求する行為だけでなく、様々な悪の根にある、不法に欲しがる心の欲望それ自体を戒めています。
ヤコブ1:14-15 人が誘惑に陥るのは、それぞれ、欲に引かれ、さそわれるからである。欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。
▽心の中の欲望にまで、律法が厳格に適用される時、生涯の中で完全にそれから自由な人はいないでしょう。しかし、それが健全な社会の土台となることであり、私たちは絶えず主イエスの恵みに立ち帰り、心の内を整え・新たにされ・洗い清めて頂いて、神の教えを自分の基準として歩んでまいりましょう。律法によって示された神の恵みに生きる人の青写真を、悔い改めと信仰を通して、聖霊の働きによって私たちの内に形作って頂くことが、神の祝福を受ける真の道です。
◆愛の教え
今日は十戒を読んできましたが、もう一度、主イエスが律法を要約された愛の戒めを思い起こしましょう。
マタイ22:37 『心をつくし、精神をつくし、思いをつくして、主なるあなたの神を愛せよ』…
マタイ22:39 『自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ』」
これらの戒めを、私たちを愛し・選び・救い・召して下さった神様からの愛の招きとして受け止めてまいりましょう。「神は独り子を賜うほどに私たちを愛して」くださり、私たちを「宝の民」・神に仕える「祭司の王国」・「聖なる国民」とするために、この聖なる律法を下さいました。▽行いによって律法を完成させようとしてはいけません。私たちをこのようにならせてくださる神の恵みを信じる信仰によって、追い求めるのです。▽まだ神の救いをはっきりと経験していない方は、この完全な律法を追い求めていく中で、「律法に到達していない、到達できない自分と、それでも愛し・選び・招いて下さる恵みの神」に出会います。それが、自分ではなく神に頼って生きるクリスチャンの人生です。その恵みの神に出会う時、完全には遠く及ばなくても、私たちを心から新たにし・清々しくし・造り変えて下さる聖霊の御業を経験させて頂くことができます。
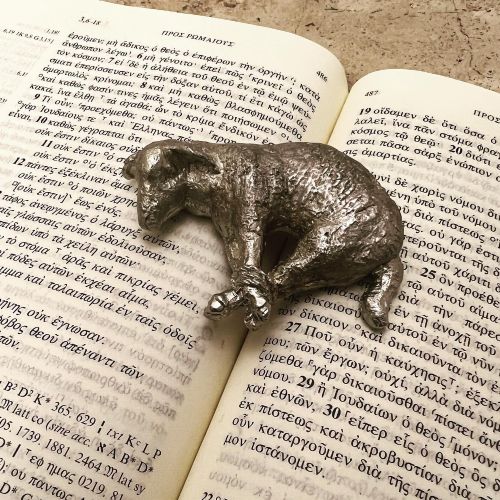
■主を畏れる心
シナイ山で神に出会った民は、恐れ、主に聞き従いました。
20:18-20 18民は皆、かみなりと、いなずまと、ラッパの音と、山の煙っているのとを見た。民は恐れおののき、遠く離れて立った。19彼らはモーセに言った、「あなたがわたしたちに語ってください。わたしたちは聞き従います。神がわたしたちに語られぬようにしてください。それでなければ、わたしたちは死ぬでしょう」。20モーセは民に言った、「恐れてはならない。神はあなたがたを試みるため、またその恐れをあなたがたの目の前において、あなたがたが罪を犯さないようにするために臨まれたのである」。
主がご自分を現されたのは、震え上がらせるためにではなく、主を恐れて罪から離れ、祝福の道を歩ませるためでした。主は私たちが、敬虔な恐れをもって、同時に神の愛への信頼と感謝をもって、慎み深くしかし信仰をもって主に従うことを喜ばれます。もし私たちが何か間違っていることがあるなら、そのことも聖霊が教えてくださいます。私たちは、これまでに自分に示され教えられてきたことに忠実に従いながら、まだ理解していないことがたくさんあることも絶えず認めて謙遜に求めながら、謙遜に恐れることなく従ってまいりましょう。
[1] この場面は、聖書の様々な箇所で繰り返し出てきます。たとえば、詩篇144:5-6など。
[2] 十戒の数え方は、教派によって2種類が存在する。
[3] ケルビムの像:25:18-、37:7-。ケルビムの織物:28:1、36:8。
[4] 東京ミッション研究所編「これからの日本の宣教 発想の大転換」第二部「文化脈化(コンテクスチャライゼーション) 日本における新しいパラダイムに向けて」など参照。


